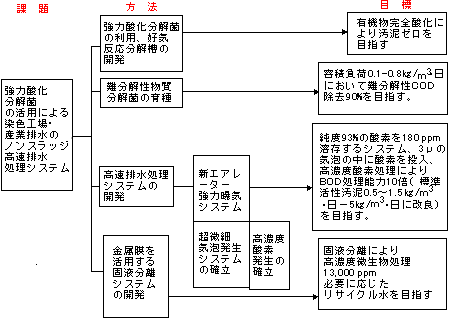従来、開放系の排水処理施設においては、その排水に特有の活性汚泥を優先繁殖させて有機物の分解処理を行ってきたが、京都大学大学院および鈴木産業は、この活性汚泥以外に、高速酸化分解菌群をベースとして排水中の有機物分解処理を行うノンスラッジ排水処理システムを開発した。
この開発は近畿経済産業局からの受託研究である即効型地域新生コンソーシアム研究開発事業の一環として産学連携で行われたもので(プロジェクトリーダー・今中忠行京都大学工学研究科教授)、高速酸化分解菌群による有機物分解処理は初めて。鈴木産業ではこの開発成果をもとに、同システムの発売を開始した。
本稿では、同システムの概要について紹介する。